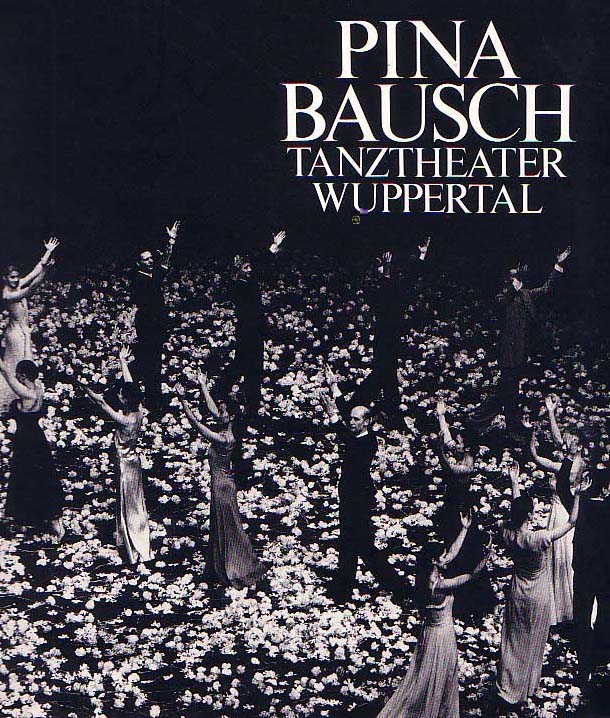現代音楽の中でのさまざまな試み―例えば、ピアノの内部にフェルトやボルトなど を詰め込んで音色を変えてしまった「プリペアード・ピアノ」や、パイプオルガンの パイプをバラバラにして各パイプに空気ポンプで空気を送って音を出す楽器、そして 医療器具や自動車の部品を太鼓やバイオリン、ハープと一緒にセットして二人で合奏 する「二人オーケストラ」などなど―これが楽器!?と驚くものまで展示されていた。 どの試みも、もとの楽器の状態にもどせるから「創造行為である」と企画者は言う。 破壊されたグールドのピアノは決して復元できないのだとも。
オランダは、現代の芸術活動に理解の深い国と常々聞いている。こんなユニークな 企画からも国民性がうかがえる。