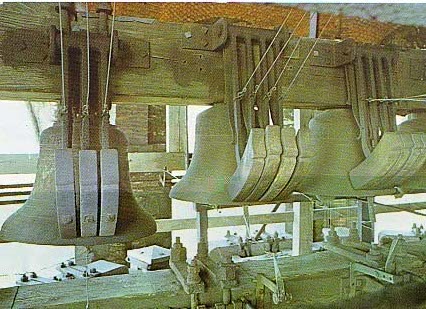この夏、学会を兼ねて西ドイツ、オーストリア、ベルギー、オランダの四カ国を回った。わず か一ヶ月の旅であったが、不思議なことに蝉の声を全く聞かなかった。確かに今年の欧州の一部は 異常気象で、寒い夏が続いていたけれど、大都会を訪れたわけでもなく、山の中の小さな町や、木 々に囲まれた小都市が多かったのに、八月上旬の暑い日差しの中でも山や木立は静けさを保ち続け ていた。
私たちは、季節の移り変わりを自然界の音で知る。ウグイスのさえずり、カエルの声に虫たちの 声。そして雨音や雪雷…というように。私たちにとって当たり前の音が、似かよった風景の中で聞 こえてこないと、心落ち着かなくなってくるから不思議である。暮らしの中にある音感覚が、私た ちの心の部分にまで影響を与えているからであろう。日本の音を聞くと、その響きの中に風景が見 えてくる。

「鳥や虫の鳴き声を出す
竹笛のいろいろ」